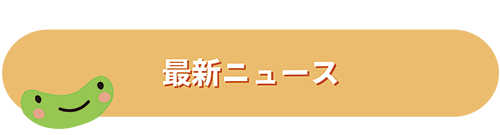-
- 2024/04/19
- ケアマネ法定研修 受講料全額補助 武蔵野市 人材確保・定着支援で申請電子化も
-
- 2024/04/12
- 施設にも車いす選択の自由を!
-
- 2024/04/05
- 働きながらヘルパー育成 東京都 訪問介護採用応援事業開始 4月15日まで事業者公募
-
- 2024/03/29
- 外国人訪問介護を拡大 厚労省 特定技能・実習生も可能に
-
- 2024/03/22
- オンラインモニタリング 初回は利用者宅訪問を 厚労省 介護報酬改定告示、Q&A発出
-
- 2024/03/15
- 配分ルール緩和で特定加算取得へ 厚労省 介護報酬改定の通知案公表
-
- 2024/03/08
- 政令市の9期介護保険料 20市平均で6693円 本紙調査 全市が準備基金を活用
-
- 2024/03/01
- 2交替夜勤が8割 医労連23年介護 施設夜勤実態調査 GH・小多機は1人体制
-
- 2024/02/23
- 成年後見制度、見直しを諮問 法務省 後見人交代や終了可能に
-
- 2024/02/16
- 地域包括医療病棟を創設 24年度診療報酬改定答申 高齢救急患者を受け入れ
-
- 2024/02/09
- 訪問介護報酬下げ「撤回を」 ヘルパー・事業者らが声明 「ありえない」怒りと失望
-
- 2024/02/02
- 厚労省 外国人訪問介護 「初任者研修修了で解禁」も
-
- 2024/01/19
- 介護報酬改定 運営基準の改正を答申 厚労省 生産性向上や負担軽減狙い
-
- 2024/01/12
- 介護関連各予算、総じて減額 老健局24年度予算案 介護保険総費用は14兆円
-
- 2024/01/01
- 目指そう「人を幸せにする介護」 ~1人ひとりに意味のある人生を~
-
- 2023/12/14
- 介護報酬改定 審議報告書取りまとめへ 給付費分科会 人材確保対策「生産性向上」で強化
-
- 2023/12/07
- ケアマネ担当件数増へ 厚労省 基準改正案 パブコメ 配置基準緩和は「見切り発車」
-
- 2023/11/30
- BCP未策定で報酬減算 厚労省提案 26年度末まで経過措置 運営基準違反で指導も
-
- 2023/11/24
- 介護報酬大幅増求め決議 介護19団体が決起集会 「安心して働ける業界に」